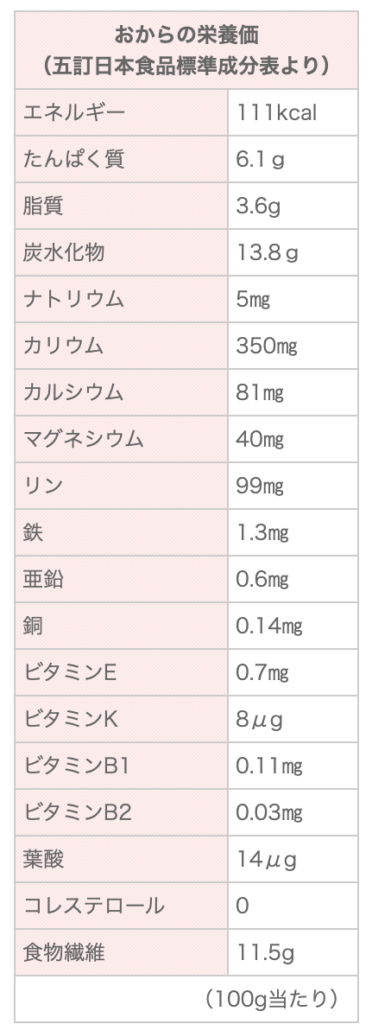脱炭素社会への架け橋
学校教育
沖縄国際大学 経済学部 地域環境政策学科の生徒を中心に、学部内外、学年問わず
「脱炭素、環境、再生可能エネルギー、カーボンニュートラル」に関心のある生徒が集まったゼミ。
授業内では、生徒一人一人が自分でプロジェクトを創出し、毎週授業で提案発表を行っています。
今回は、その集大成として【脱炭素チャレンジカップ2025】にゼミ生でチームとしてエントリーしました。
脱炭素チャレンジカップとは、CO2排出量の実質ゼロを目的とした地球温暖化防止に関する地域活動について、優れた取組を表彰している全国大会です。
学校・市民団体・企業・自治体など全国から多数エントリーし、名称を変えながらも14年目、これまでのエントリー総数は11,245 件にもなります!
生徒たちの探究心と小山先生の熱心な指導のもと、国内最大規模でハードルの高い大会にて、全国から集まったライバルたちに負けず見事アイデア賞を受賞!!